
アタラクシアのことを考え作品にする前に、岩波文庫「エピクロス – 教説と手紙 – 」に一度目を通した。読んでみると自分の考えていることと似通っていたり納得できることが記されていたため、正直もうこれを額装して展示すればいいのでは、と半月ほどはそう考える内容でしばらく描くことができなかった。せやせやと頷きながら読み進めていると突然ハシゴを外されていることに気づく。気持ちよく読むには注意が必要なものではあるが。

読んだがためあれこれと考えることになったのだけれど、アタラクシア=平静・平穏という解釈であったのならここまで深く悩m考えることはなかったかもしれない。
まず、見る側にアタラクシア(平静さ)を与えるということは不可能だと思った。私はいつだって作品を目の前にすれば動揺/心を動かされてきた。その色彩の驚き、画家の筆のタッチひとつひとつを追い、画面のマチエールを感じ、構図に気付かされ…それらを感じれば大なり小なり何か動かされるものが生まれるものであるのだから。
”心境の平静と肉体の無苦とが、静的な快である。これに反し、喜びや満悦は、動的な現実的な快と見なされる。”
これからのことを考えることや将来の夢、こうでなくてはならないと理想を持つことは生きる上で重要なものであると同時にアタラクシアからは遠ざかるものでもあるように思う。何かに抵抗する/受け入れない、反することはアタラクシアからは遠い。私もいつの頃からか平静というものを知らない、生活の中で見当たらないものになっている。瞑想したときのような感じだろうか。今の自分は常に何かに迫られ追いかけ刺激を受けることでなんとか立っていられる/それらに支えられているようなところがある。
改めてアタラクシアを考えた時、花が咲くようなことだろうかという思いが湧いた。次のために咲く、咲いたら当然枯れる、また翌年も当然のように咲くために咲いては枯れるというサイクルはなんだか美しい。こうなりたい・個人主義となった人間とは対照的である。
”必然は悪である。だが、必然にしたがって生きることには、何の必然もない。”
花はほとんど描いたことがなかった。描いたことはなかったけれど、ずっと悩みながらやっていればそのうちにいろんなことを教わる/気づく。そうするといつできるのかも大体わかってくるので、できないという悩みも不安も、期限/締切について焦る必要もなくなり落ち着く。感動/動きは求めるけれど、一方では静かなもの/状態でいる時というのが一番心地がいい。それをアタラクシア/平静や平穏と呼ぶべきかはわからないが。何かと繋がっているような、いつもそんな喜びや安心感がある。
花といえば、世阿弥の「風姿花伝」の時分の花を想う。決して今の自分に満足しているわけではない、とてもよくできたというわけではない、明日はまた違っているだろうといつも考えている。それでも今でなくては描けないという喜びは生まれるものだ。花を描いてみると、こうでなくてはならないという固まったイメージや思いから遠ざけてくれる。花はこう描かなくてはならないという人はたくさんいるだろう。正直そんなことはどうでもいい。他者の気持ちを理解できるわけではない、花の気持ちなどわからない。だからこれでいいと思った。
エピクロスを読んで描くことに迷った時、以前手に入れた「美術の力」を開くことになった。

”いったい、美術にどれほどの力があるのだろうか。 心に余裕のある平和な者には美しく有意義なものであっても、この世に絶望した、終わった者にも何か作用することがあるのだろうか。”
私には他者にアタラクシアを与えることはできない。私のやってきたことの結果/痕跡だけを見てもらうだけである。「エピクロス」を読んで実践してくれというほかない。もしかしたら、反発などせず全て人の言いなりになって従っている方が平穏・平静な生活を送れるのかもしれない。抗うことは辛いもの。宗教や政治家、他者/外側にではなく自分のやっていること/自分を信じることができたなら、その時こそアタラクシアに至らしめるのではと思っている。自分がまた、今度はもっと絶望した時、それができるかはわからない。
苦しかった。毎日逃れたかった。しかしそれでもまた描かなければならない。
これまで自分が作品に求めてきた静けさは平静さではない。平静というよりはもっと違う、静寂やその類なのだろう。静謐や閑寂など静かさを示す/言い表す言葉はいくつもあるが、どれもがそれぞれに違ったもの/イメージとして在ることに気付いた。それは私にとってとても興味深く面白いものであった。
———————————————————————————
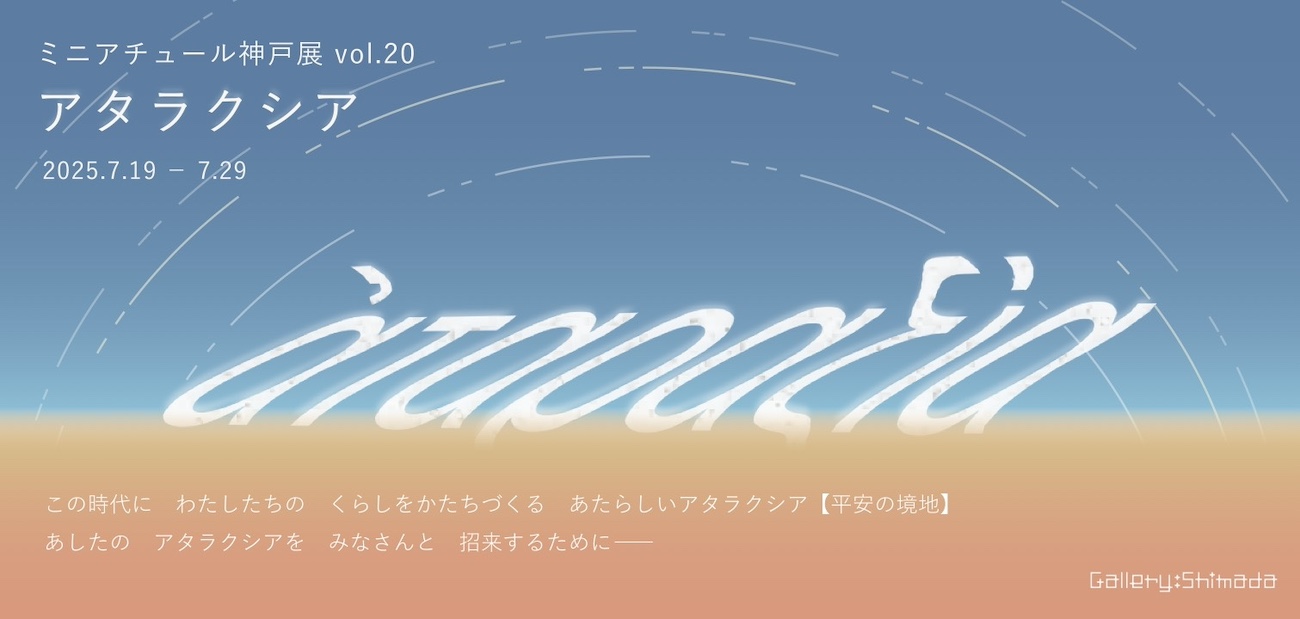
コメントを残す